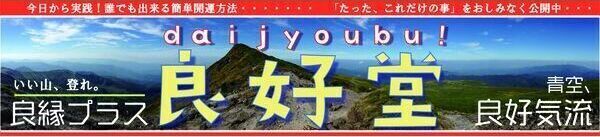
尊き松の存在②
以下は、須山定義・北川泉 著者 「松と日本人」 (平成元年発行)
より抜粋しております。
松は一般に杉や檜に比べて天然更新力が強く、乾燥にも耐える陽樹で
花崗岩の風化土壌などのやせ地や火災跡地など他の樹種が生育しないような
土地でもよく優先種になる。
松の特徴は、水に大変強く、出雲では水道管に生松の赤味を使用していた。
杭に使用しても水気のある場所に強く、乾燥地では長持ちしない。
昭和10~15年頃には舟材として使用されていた。
針葉樹の中で燃やして最も火力が強いのが松であることから、
古くから家庭用の燃料となり、たたらや製塩、窯業などに大量消費されてきた。
材木といえば、ヒノキやスギ、ケヤキなどがよく知られているが、
マツも材木としても使用されてきた。
例えば、島根県松江市にある神魂神社は、1346年に建立され国内では最古の大社造り
とされており、その社殿(国宝)の柱、床、階段が黒松で作られている。
出雲大社本殿にも柱が左右6本の高さ八間半(約15.3m)の直径二尺四寸四分
(約7.3cm)と、前後中央の中柱が八間半の二尺八寸の白太を除く丸木中味材の松の柱
(出雲地方産出の黒松のようである)によって建築された。
松の銘木として評価を高めたのは、新宮殿の造営に松が大量に使用されたこと。
マツは材木としても大きな役割を担ってきた。

松は、樹齢が2、30年になると根元に松茸などの菌が増えてくる。
その後数十年はキノコを生やす時期で、毎年少しずつ拡大するが、
松茸が出なくなると菌は死んで残骸が灰のようになって残る。
すると、水通しが悪くなってその下の土壌は変化して松の勢いをそぐ結果になる。
松の樹齢が50年過ぎると菌も変化してシロ(菌のつく場所)がなくなり、
松林の下にはウルシなどの落葉低木やヒサカキといった常緑低木、シイなどの
高くなる常緑樹も目立つようになる。
7、80年になると、赤松の劣精木は間引かれたように少なくなって、
松林は明るさを増してくるが、それによって林に混在していた広葉樹が勢いづいてくる。
樹齢100年になると赤松と広葉樹との混交林となるが、赤松は次第に減り
反対に広葉樹の方が勢いが良くなる。
赤松は200年くらいで多くは老化、枯れ木となってゆく。
赤松林の森林の生態系がゆっくりと進化、変化するに伴って赤松の生存に合わなくなってくる。
同時に松どうしの競合といった面も見られるようになり、生き残った松はヒョロ長で
枝葉が上まで枯れて風雪に弱くなる。
それらの淘汰に耐えて、300年〜500年と生長した松は赤味の多い銘木となるのである。
※出雲大社は60年に1度遷宮が行われ、2013年(平成25年)に御本殿は
新しくなっておりますので、現在も松が使用されているかは不明です。

#松#赤松