良好堂へようこそ
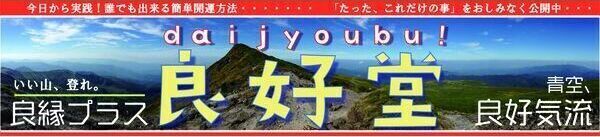
神が宿る木
荒れた浜などに、他の樹木にさきがけて根をおろし、生育する松に対し、
古代の人々は畏れと尊敬の念を抱いた。
「常陸国風土記」に
「浜の松の下には、泉が湧きだしており、その水は非常にうまい」
と記されているように松に山野の霊が宿ることを知り、神格化が始まっている。
常陸国那賀郡の賀毘礼の高い峰には、天つ神の系統の立速日男命、
またの名を速経和気命という神がおられる。
もともとこの神は松沢というところの、枝のたくさんある
松の木の八俣においでになっていたが、祟神で、
この松の木に向かって大小便をすると必ず病気をしたという。
近くの人は困って、朝廷に申し上げ、うやうやしくお祭りし、
「この地はきたなく、臭く、神様の地にふさわしくありません。
清浄な高い山へお避けください」
と丁重に、高峰に造った社に移っていただいた、
と「常陸国風土記」は記している。
ここにも、松は世俗の地にあっても、清浄で、
その清浄さは神さえ宿ることができる
という信仰があったことが示されているのである。
有岡利幸 著者 「松と日本人」 より

#松#赤松