良好堂へようこそ
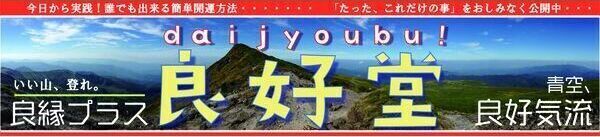
江戸時代の森林保護
徳川幕府のもと各藩とも山林資源の保護、育成に努めたとある。
当時はマツ、スギ、ヒノキ、ケヤキ、ツガ、サワラ、モミ、ウルシ、キリ、
クスなどが禁木とされ、特に木曾の五木とされるヒノキ、サワラ、
アスナロ、コウヤマキ、ネズコを盗伐した者は打ち首、枝木を伐った者は
片腕を落とされたと言われている。
承応三年(1654年)の大洪水と凶作は、洪水の原因が山の荒廃にあるとして
治山治水の重要性を説き、山林の乱伐禁止、建材などの等級、薪炭の節約、
大自然の摂理に従った山林の取り扱い、時をえて山に入るようにとされた。
ある藩では一つの山を20ブロックに分け、毎年1ブロックの20年生ぐらいの
広葉樹の木を伐り、薪炭として売り、これを毎年繰り返すことで、
山林を荒廃させることなく保たせることが出来たとある。
活用するだけでなく、如何にして森林を守るか当時も深刻な状態で
あったと思われる。
現在は、その逆ともいえる活用されないことによって、
森林が荒れ地化が進んでいる。
参考文献 須山定義・北川泉 著者 「松と日本人」 より

#森林#森林保護