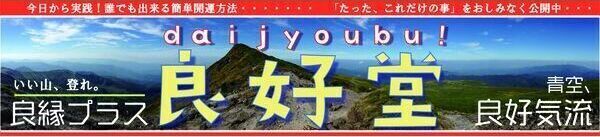
赤松の働き
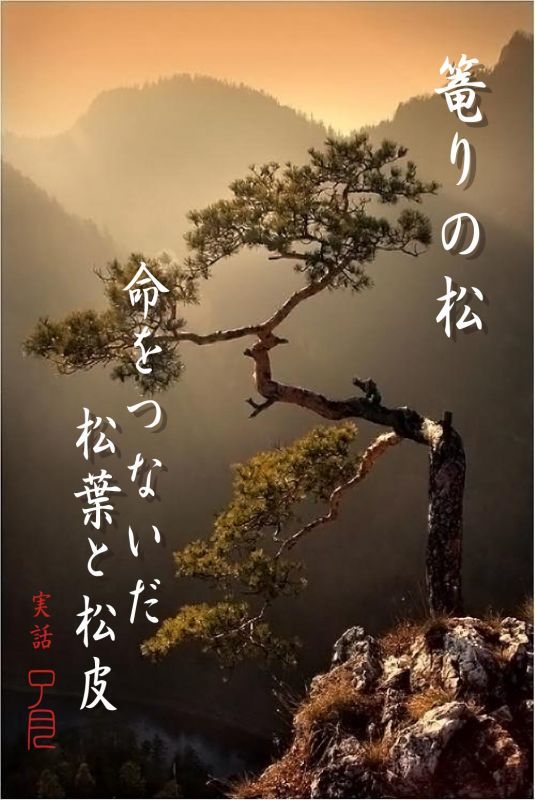
赤松の効果①
<血管・血液の病や鎮痛効果、長寿のために>
血管、血液の病で苦しんでいる方にお伝えしたい赤松の存在。
昔、仙人が山修行する時、穀物を断って赤松の葉を食していたことが
書物にも残されており、漢方の医学書にも記されています。
修験者や僧侶の修行中の常食であり、長寿の漢方薬とも言われてきました。
赤松を食すことで体が軽くなり、行に入る上で身体を清める力があり、
現代においても修験者が山修行の際には赤松の葉や幹を食すことが
引き継がれています。
赤松の葉には優れた栄養があり、山で遭難しても赤松の葉を食べていれば
生き延る事が出来ます。
赤松は、血液を綺麗にし、血管を強くする働きがあり、
血管の病(脳梗塞、心筋梗塞、狭心症、動脈硬化、癌など)によいとされ、
鎮痛効果があることで、神経痛、関節痛や頭痛、リウマチの人にも
また血流が良くなることで冷え症にも効果があると言われています。
その効能の高さから、万能薬と言われておりました。
赤松の働き②
あらゆる病で苦しむ人達に知って欲しい赤松の存在。
松という名は、『天から神が降りてくるのを待つ』ことからその名がついた
とも言われており、昔から御神木として祀られてきました。
松は古き時代から神聖なるものとされ、門松や松竹梅などめでたいものとされ、
また松は邪気を祓うとされてきました。
土が余りない岩山や海辺の厳しい環境でもどっしり構える黒松とは反対に
優雅な舞いを連想させるくねりと、柔かい印象を持つ赤松は女松とも称され、
松の中でも赤松は食することで、心臓や血管を強くし、血流を良くし、
古来より民間療法としても用いられてきました。
西洋医学が取り入れられるようになってから松による治療法は
薄れていきましたが、現代病においても大きな存在と言えるでしょう。

赤松の働き③
天然素材の素晴らしいところは、薬と違い副作用がないこと。
生きた細胞を活性化する働きがあり、自己治癒力を高めてくれます。
血液は食べた物でつくられている為、食べた物によっては
血流が滞ったり、だるさや冷え、痛みなどに繋がる場合があり、
体調不調の原因となります。
日常において乱れた食生活を継続していれば、
松の効果もわかりづらいかもしれません。
和食中心の食事に切り替えながら、赤松を摂られることをお勧めします。
生松をかじるのも良いですし、乾燥させたものをお茶としていただくのもお勧めです。
その際は茶殻の葉っぱも摂られると尚良いかと思います。
松にはデトックス効果があるとされ、禁煙飴などにも使われております。
喫煙者の方にとっても有効的と言えるかもしれません。

赤松の働き④
以下は、『女松の会』 HPの「松葉で症状別の処理方法」より抜粋させていただきました。
病気・症状 | 松葉の処理方法(58ページ) |
| 高血圧症 | ・松葉をひとつかみ煎じて(煮詰めて)お茶代わりにする ・松葉50本ほどを水洗いし、1cmほどの長さに切り、すり鉢に 入れて、杯2杯の水を加えてする。その松葉液をふきんで こして絞り出し、1日3回空腹時に飲むと効果的 ・松葉を噛む |
| 心筋梗塞 | ・松葉液を1日3回に分けて空腹時に飲む (若松葉取ってひとつかみを水洗いし、1センチほどの長さに切り、 すり鉢に入れて、杯2杯の水を加えてドロドロにする それをふきんでこすと松葉液ができる) ・松葉を噛む |
| 心臓が弱い・心臓病 | ・松葉を噛む(若芽を生で噛んで汁を吸う) ・松葉風呂に入浴する(新鮮な松葉50〜100gとよもぎの葉、 ヤナギの葉を小袋に詰め湯舟に入れて入浴する) ・松葉酒もよい |
| 中風 | 特に舌がもつれた場合は ・雄松の葉の細切りを酒で煎じて(煮詰めて)その酒を飲む 松葉の量は20g、お酒は5合、これを半分になるまで煎じつめ、 少量ずつ飲む ・予防に松葉を毎日噛む |
| 脳嗌血 | ・雄松、シェロ葉、大豆各20gを合わせて煎じて(煮詰めて)飲む、 頭に汗が出るとよい |
| 動脈硬化 | ・松葉をひとつかみ濃く煎じて(煮詰めて)飲む ・松葉を噛む(毎日50本ほどの松葉の若芽を水洗いして噛み、 出た汁を飲む) ・松葉酒を毎食前、及び食後に杯1〜2杯飲む |
| 脳梗塞 | ・松葉、シェロ葉、大豆を煎じて(煮詰めて)飲む ・松葉を噛む(にじみ出る汁を飲み下していると、血栓を浄化して 塞栓を防ぐ効果がある) ・松葉をひとつかみ煎じて(煮詰めて)飲む |
| 便秘 | ・松葉を噛む(松の木の下部に生えている太い松葉を噛む)
|
| 急性胃炎 | ・陰干しした松葉10gを300mlの水で半量に煎じつめ、1日3回、 空腹時に服用する |
| 下痢症 | ・松葉の液を飲む
|
| 糖尿病 | ・のどが渇く時に松葉液を飲む(赤松の生葉をすり鉢でつぶし、 にじみ出た汁を飲む) ・松葉4分、檜(ひのき)の新芽の青いのを6分の割合で煎じて (煮詰めて)飲む。その際肉食は避ける |
| 二日酔い | ・赤松の葉をひとつかみ煎じて(煮詰めて)飲む
|
| 喘息 | <神経性喘息> ・松葉の新芽を黒焼き(黒焼きとは:http://is.gd/gkM6aB) にして、その粉末をのどにつける ・雄松葉の陰干しを1日20g煎じて(煮詰めて)飲む <気管支喘息> ・新鮮な松葉をひとつかみ煎じて(煮詰めて)飲む |
| 膣炎 | ・松葉を煎じた(煮詰めた)お湯で腰湯をする
|
| アレルギー性鼻炎 | ・新鮮な松葉をひとつかみ煎じて(煮詰めて)飲む ・陰干しにした松葉を20g煎じて(煮詰めて)飲む |
| 慢性アルコール中毒 | ・松葉をひとつかみ煎じて(煮詰めて)1日3回飲む
|
| 眼底出血 | ・松葉を1日20g煎じて(煮詰めて)飲む
|
| 口臭 | ・松葉を噛む(数本)
|
| 痛風 | ・松葉の煎汁から葉を取り除き40度くらいの温湯中に痛む 手足をつける |
| ストレスからくる諸症状 | ・松葉風呂に入浴する |
| リューマチ | ・松の若葉を煎じた(煮詰めた)汁で温める ・松葉液を飲む(盃に1、2杯毎食前に飲む) |
| 肺結核 助膜炎 | ・松の新芽の花粉がすっかり出尽くしたころを陰干しにして 煎じて(煮詰めて)飲む |
| 潰瘍 | ・生の松葉をひとつかみ煎じて(煮詰めて)飲む ・陰干しした松葉をひとつかみ煎じて(煮詰めて)飲む |
| 口内炎 | ・松葉液を脱脂綿に含ませ、幹部に当てる
|
| 神経痛 | ・松葉液を飲む
|
| 腰痛 | ・松葉をひとつかみ煎じて(煮詰めて)飲む
|
| 肩こり | ・松葉をひとつかみ煎じて(煮詰めて)飲む(お茶代わりに)
|
| 歯ぐきの腫れ | ・松葉の煎じ汁に塩を加えて飲む ・松葉を黒焦げに焼いて痛む葉に詰める ・青松葉を数本一緒に噛みしめる |
| 歯槽膿漏 | ・松葉をひとつかみ400mlの水で半量に煎じつめ、 体温程度まで冷ましてからうがいをする ・松葉液を脱脂綿に含ませ、患部に当てる ・松葉を数本一緒に噛みしめる |
「松葉健康法」高嶋雄三郎著書(松葉を食べる会の会長)から

| 病気・症状 | 松葉の処理方法(63ページ) |
| 心臓 | 松葉・樹脂・あま皮などを煎じて(煮詰めて)お茶代わりに飲む |
| 高血圧 | 松葉・樹脂・あま皮などを煎じて(煮詰めて)お茶代わりに飲む |
| 貧血 | 松葉・樹脂・あま皮などを煎じて(煮詰めて)お茶代わりに飲む |
| 神経痛 | 松葉・樹脂・あま皮などを煎じて(煮詰めて)お茶代わりに飲む |
| リュウマチ | 松葉・樹脂・あま皮などを煎じて(煮詰めて)お茶代わりに飲む |
| 老人ボケ防止 | 松葉・樹脂・あま皮などを煎じて(煮詰めて)お茶代わりに飲む (脳の働きが良くなる) |
| 肺結核 | 松ヤニを粉末にして、1日1回小さじ半分くらいを含んでいると良くなる |
| 声がれ | 生松葉を軽くひとにぎりくらい噛んでその汁を飲む |
| 歯痛 | 生松葉を10本内外噛み砕いて噛み締めておく(10分くらいでよくなる) 又は、松ヤニを虫歯の穴に詰める |
| 不老長寿 | 黒ゴマ、黒豆を等量づつ煎り、それを粉末にして、さらに松葉を黒豆の 半量くらいを粉末にして加え、これを茶さじで一杯ずつ飲む |
「趣味の薬草」高橋貞夫著書(漢方薬草園芸士)から

赤松の働き⑤
■ダイエットに繋がる働き
赤松には血流を良くする効果があります。
血流が良くなれば、体に栄養が運ばれやすくなり、代謝が上がり、
代謝が上がることで体温は上がり、脂肪燃焼しやすくなります。
食事制限だけをしていると、筋肉が落ち、基礎代謝が低下し、
エネルギーが燃焼しづらくなることで、リバウンドを起こす原因と言われています。
筋肉を付けたり、維持する為にアミノ酸が必要とされていますが
赤松の葉には9種類の必須アミノ酸と人間の体内で合成される11種類の
非必須アミノ酸が全て含まれているというデータから
赤松は添加物が含まない天然のスポーツドリンクと言えるでしょう。
■便秘改善に繋がる働き
身体の冷えは、腸の血行を悪くし、腸の働きを鈍くしてしまいます。
血流を良くし、冷えを改善することによって、腸の活動が活発になり、
赤松の葉そのものを摂ることで、食物繊維も摂ることが出来ます。
■若返りに繋がる働き
赤松には、血流促進の効果以外に血管を強くする働きがあると言われていました。
血管は若いうちは新しいゴムのように弾力に優れていますが
運動不足や年齢に伴い老化していくと伸び縮みしなくなり、弾力が失われていきます。
硬くなった血管は動脈効果のリスクが高まると言われています。
心臓や脳の血管が詰まれば、狭心症、心筋梗塞、脳梗塞、脳出血に。
頭皮の血管が詰まれば抜け毛の原因に。
皮膚の血管が詰まればシワの原因になります。
血流を促進し、血管を若く保つことは、健康でいられるだけでなく
若さを保つことにも繋がると言えるでしょう。

#赤松#赤松の効能
